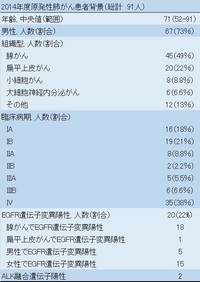2017年07月28日
周術期化学療法におけるがん薬物療法専門医の役割
2017年7月28日 日本臨床腫瘍学会総会2日目(神戸市)
会員委員会企画
周術期化学療法におけるがん薬物療法専門医の役割
・・・結局のところ、各病院でルールを決めて取り組むべきことだ。
呼吸器内科医と呼吸器外科医は同じ呼吸器センターで働いていることが多いが、腫瘍内科医と呼吸器外科医は必ずしもそうではない。
いつも近くにいるかいないかというのは、結構大きな違いだと思う。
多分、他の領域でもそうではないだろうか。
「いつでも、face to faceで気楽に相談できる」というのが何より大切なのだ。
MMP1-1
外科系薬物療法専門医の立場から
・大きな大学病院の消化器外科医の先生が発言
・消化器外科系の臨床試験は術式検討のたゆまぬ繰り返し
・より低侵襲に、より効果的に
・外科医の殆どは、切除範囲を広げても癌は取り除けないし、治療成績は高まらないと漠然と考えている
・消化器外科の術前・術後には、消化器外科医でないと対応できないようなさまざまな合併症が待ち受けている
・諸問題に対応しようと思ったら、消化器外科医が薬物療法に習熟して一貫した治療を行うのが理にかなっている
MMP1-2
内科系薬物療法専門医の立場から
・大きな大学病院の腫瘍内科主任教授、臨床腫瘍学会のone of the leaderが発言
・外科とか内科とかこだわらず、それぞれの得意分野を活かしてチームとして取り組みましょう
・臓器横断的に、幅広い知識を有する臨床腫瘍医が治療に携わることは、メリットが大きい
・日本と韓国が一緒にやった、肝細胞がんに対するsorafenib療法の検証的試験
→日本では標準治療と差が出ず、韓国では圧倒的な差がついた
→患者背景も治療法も差がなく、唯一差があったのは、日本では非腫瘍内科医が、韓国では腫瘍内科医が患者を担当した
→日本の方が累積投与量が少なく、治療期間も短かった・・・有害事象をうまくマネジメントできなかったことが原因では?
・がん薬物療法専門医はそれなりに増えてきた
総数:1229人
都道府県がん診療拠点病院に在籍:326人(26.5%)
地域がん診療連携拠点病院に在籍:527人(42.9%)
がんセンターに在籍:55人(4.5%)
その他の病院に在籍:288人(23.4%)
病院以外に在籍(政府機関、研究機関、海外留学中など):33人(2.7%)
・都道府県がん診療連携拠点病院全49施設の中で、
がん薬物療法専門医がいない病院:1施設(2%)
がん薬物療法専門医が1人しかいない病院:3施設(6%)
がん薬物療法専門医が2人しかいない病院:8施設(16%)
がん薬物療法専門医が3人しかいない病院:6施設(12%)
→全体の1/3では専門医が3人以下
・地域がん診療連携拠点病院全350病院中、がん薬物療法専門医がいない病院は151施設(43.1%)
MMP1-3
呼吸器内科系薬物療法専門医の立場から
・首都圏のがんセンターに勤める肺癌領域のone of opinion leaderが発現
・先にしゃべった二人の演者、どちらにも賛成できない
・薬物療法の実務は、各臓器専門の腫瘍内科医が担当すべきだろう
・そもそも肺癌は、全体の75%が治癒不能で、外科医の出る幕はない
・術後補助化学療法を内科に依頼するにあたり、術後の5年生存割合や術後補助化学療法に期待できる効果について説明していない外科医が結構いて、信用できない
・プラチナ併用化学療法やUFTの術後補助療法なら、マンパワーがある程度ある外科ならできなくはないだろう
・術前化学療法となると、許容できる毒性や手術のタイミングを測るために、内科医と外科医の密な連携が欠かせない
・術前治療にこだわりすぎて、手術が出来なかったらなんにもならない
・今後周術期に抗がん薬、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬が導入されたら、多分外科医では管理できなくなる
MMP1-4
皮膚科の立場から
・中部地方のがんセンターに勤める皮膚科医が発言
・皮膚科医は、免疫チェックポイント阻害薬を扱うようになって、考え方も考えられ方も変わった
昔の皮膚科医:
独自性が高く、閉鎖的な考え方を持ち、チーム医療には消極的
今の皮膚科医:がん薬物療法専門医のサポートをすることが多くなった
チーム医療に組み入れられるようになった
いろんな治療を見て、薬物療法への理解が進んだ
悪性黒色腫の治療を介して、他の診療科との連携が進んだ
がん薬物療法に対しては、駆け出し者の立場
昔の腫瘍内科医:
皮膚領域に対する関心が少ない、皮膚合併症は見過ごしがち、チーム医療には積極的
今の腫瘍内科医:
皮膚科医の治療をサポートしてくれる(治療選択、用量設定、有害事象管理など)
悪性黒色腫の治療に免疫チェックポイント阻害薬が導入されたことで、皮膚科領域への注目度が高まった
悪性黒色腫の患者の管理を手伝って、経験をつんで、自分たちの治療に活かそうと目論んでいる
あわよくば、悪性黒色腫の治療も皮膚科医から奪おうとしているきらいがある、縄張り荒らし
・免疫チェックポイント阻害薬と併用することで、皮膚合併症を起こしやすいとされる薬がある
去痰薬、プロトンポンプ阻害薬、ST合剤、抗痙攣薬、ベムラフェニブ、アレクチニブ
会員委員会企画
周術期化学療法におけるがん薬物療法専門医の役割
・・・結局のところ、各病院でルールを決めて取り組むべきことだ。
呼吸器内科医と呼吸器外科医は同じ呼吸器センターで働いていることが多いが、腫瘍内科医と呼吸器外科医は必ずしもそうではない。
いつも近くにいるかいないかというのは、結構大きな違いだと思う。
多分、他の領域でもそうではないだろうか。
「いつでも、face to faceで気楽に相談できる」というのが何より大切なのだ。
MMP1-1
外科系薬物療法専門医の立場から
・大きな大学病院の消化器外科医の先生が発言
・消化器外科系の臨床試験は術式検討のたゆまぬ繰り返し
・より低侵襲に、より効果的に
・外科医の殆どは、切除範囲を広げても癌は取り除けないし、治療成績は高まらないと漠然と考えている
・消化器外科の術前・術後には、消化器外科医でないと対応できないようなさまざまな合併症が待ち受けている
・諸問題に対応しようと思ったら、消化器外科医が薬物療法に習熟して一貫した治療を行うのが理にかなっている
MMP1-2
内科系薬物療法専門医の立場から
・大きな大学病院の腫瘍内科主任教授、臨床腫瘍学会のone of the leaderが発言
・外科とか内科とかこだわらず、それぞれの得意分野を活かしてチームとして取り組みましょう
・臓器横断的に、幅広い知識を有する臨床腫瘍医が治療に携わることは、メリットが大きい
・日本と韓国が一緒にやった、肝細胞がんに対するsorafenib療法の検証的試験
→日本では標準治療と差が出ず、韓国では圧倒的な差がついた
→患者背景も治療法も差がなく、唯一差があったのは、日本では非腫瘍内科医が、韓国では腫瘍内科医が患者を担当した
→日本の方が累積投与量が少なく、治療期間も短かった・・・有害事象をうまくマネジメントできなかったことが原因では?
・がん薬物療法専門医はそれなりに増えてきた
総数:1229人
都道府県がん診療拠点病院に在籍:326人(26.5%)
地域がん診療連携拠点病院に在籍:527人(42.9%)
がんセンターに在籍:55人(4.5%)
その他の病院に在籍:288人(23.4%)
病院以外に在籍(政府機関、研究機関、海外留学中など):33人(2.7%)
・都道府県がん診療連携拠点病院全49施設の中で、
がん薬物療法専門医がいない病院:1施設(2%)
がん薬物療法専門医が1人しかいない病院:3施設(6%)
がん薬物療法専門医が2人しかいない病院:8施設(16%)
がん薬物療法専門医が3人しかいない病院:6施設(12%)
→全体の1/3では専門医が3人以下
・地域がん診療連携拠点病院全350病院中、がん薬物療法専門医がいない病院は151施設(43.1%)
MMP1-3
呼吸器内科系薬物療法専門医の立場から
・首都圏のがんセンターに勤める肺癌領域のone of opinion leaderが発現
・先にしゃべった二人の演者、どちらにも賛成できない
・薬物療法の実務は、各臓器専門の腫瘍内科医が担当すべきだろう
・そもそも肺癌は、全体の75%が治癒不能で、外科医の出る幕はない
・術後補助化学療法を内科に依頼するにあたり、術後の5年生存割合や術後補助化学療法に期待できる効果について説明していない外科医が結構いて、信用できない
・プラチナ併用化学療法やUFTの術後補助療法なら、マンパワーがある程度ある外科ならできなくはないだろう
・術前化学療法となると、許容できる毒性や手術のタイミングを測るために、内科医と外科医の密な連携が欠かせない
・術前治療にこだわりすぎて、手術が出来なかったらなんにもならない
・今後周術期に抗がん薬、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬が導入されたら、多分外科医では管理できなくなる
MMP1-4
皮膚科の立場から
・中部地方のがんセンターに勤める皮膚科医が発言
・皮膚科医は、免疫チェックポイント阻害薬を扱うようになって、考え方も考えられ方も変わった
昔の皮膚科医:
独自性が高く、閉鎖的な考え方を持ち、チーム医療には消極的
今の皮膚科医:がん薬物療法専門医のサポートをすることが多くなった
チーム医療に組み入れられるようになった
いろんな治療を見て、薬物療法への理解が進んだ
悪性黒色腫の治療を介して、他の診療科との連携が進んだ
がん薬物療法に対しては、駆け出し者の立場
昔の腫瘍内科医:
皮膚領域に対する関心が少ない、皮膚合併症は見過ごしがち、チーム医療には積極的
今の腫瘍内科医:
皮膚科医の治療をサポートしてくれる(治療選択、用量設定、有害事象管理など)
悪性黒色腫の治療に免疫チェックポイント阻害薬が導入されたことで、皮膚科領域への注目度が高まった
悪性黒色腫の患者の管理を手伝って、経験をつんで、自分たちの治療に活かそうと目論んでいる
あわよくば、悪性黒色腫の治療も皮膚科医から奪おうとしているきらいがある、縄張り荒らし
・免疫チェックポイント阻害薬と併用することで、皮膚合併症を起こしやすいとされる薬がある
去痰薬、プロトンポンプ阻害薬、ST合剤、抗痙攣薬、ベムラフェニブ、アレクチニブ
2022年01月06日の記事より・・・各種マスクによる新型コロナウイルス拡散予防効果
2022年01月02日の記事より・・・新年を迎える幸せ
お引越しします
追憶
肺がん患者に3回目の新型コロナウイルスワクチン接種は必要か
そろりと面会制限の限定解除
新型コロナウイルスワクチンの効果と考え方
新型コロナワクチン感染症が治った人は、ワクチンを接種すべきか
抗がん薬治療における刺身・鮨との付き合い方
広い意味でのチーム医療
病院内におけるワクチン格差のリスク
順序
2015年度のデータベースから
2014年度のデータベースから
2013年度のデータベースから
2012年度のデータベースから
2011年度のデータベースから
2010年度のデータベースから
2009年度のデータベースから
2008年度のデータベースから
2022年01月02日の記事より・・・新年を迎える幸せ
お引越しします
追憶
肺がん患者に3回目の新型コロナウイルスワクチン接種は必要か
そろりと面会制限の限定解除
新型コロナウイルスワクチンの効果と考え方
新型コロナワクチン感染症が治った人は、ワクチンを接種すべきか
抗がん薬治療における刺身・鮨との付き合い方
広い意味でのチーム医療
病院内におけるワクチン格差のリスク
順序
2015年度のデータベースから
2014年度のデータベースから
2013年度のデータベースから
2012年度のデータベースから
2011年度のデータベースから
2010年度のデータベースから
2009年度のデータベースから
2008年度のデータベースから
Posted by tak at 15:28│Comments(0)
│その他